飼料価格が上がり続けている。要因は多岐に亘り、円安、コロナ、ウクライナ、中国の旺盛な需要、肥料の値上がり、コンテナ不足、海上運賃の値上がりなどなどで、大豆もトウモロコシも粗飼料も右肩上がりだ。そこで国産飼料に期待がかかるが、中でも粗飼料の代替となるWCS用稲は、米価下落の中、水田での収益機会拡大に繋がり、生産過程も通常の水稲と重なり、生産者としては大きなメリットがある。
そこで粗飼料がメインとなる和牛繁殖農家を訪ね、稲WCSの取り組みを聞いた。現場ではタカキタの可変径ロールベーラVC1620WNが使われ、耕畜連携を推進する機械として頼りにされていた。
稲WCSメイン粗飼料にして肉用牛の繁殖経営を展開
輸入粗飼料の価格が上がっている中、「粗飼料づくりを続けてきて良かったと思っています」。そう話すのは今回お訪ねした横田照夫さん(72歳)。四国の最東端に位置する徳島県阿南市で、和牛の繁殖経営に取り組んでいる。
横田さんは現在、フリーバーン牛舎で90頭の母牛と40〜50頭の子牛を飼育。年間約60頭の子牛を生後9ヵ月で出荷している。元々酪農を行っていたこともあり、その頃から粗飼料は全て自給。牛舎の仕事は一人で行い、粗飼料づくりは親族や知人の手を借りる。
粗飼料は稲WCSが中心。「和牛の繁殖は牛を健康に育てることが重要です。そのため産前産後だけは配合飼料を与えますが、後は粗飼料だけの給餌です。牛の健康を維持するのに繊維質が多い稲WCSは向いています」。耕畜連携により40haの水田で依託生産している。「田植えや栽培管理は耕種農家にお願いし、収穫作業はこちらが行って稲WCSに調製します。収穫後は牛の堆肥を水田に還元し、地域内の循環型農業を構築しています」。その他、15ha程の河川敷に生えている野草を収穫して粗飼料にしている。
「WCSの取り組みを始めたとき、農家の人はWCSについて何も知りませんでした。もちろん交付金が出ることも。その中で、1軒の農家を何とか説得して、この耕畜連携をスタートしました」。最初の年は5〜6haの規模で、そこから参加する農家が増え、現在の規模となり、さらに増え続けている。
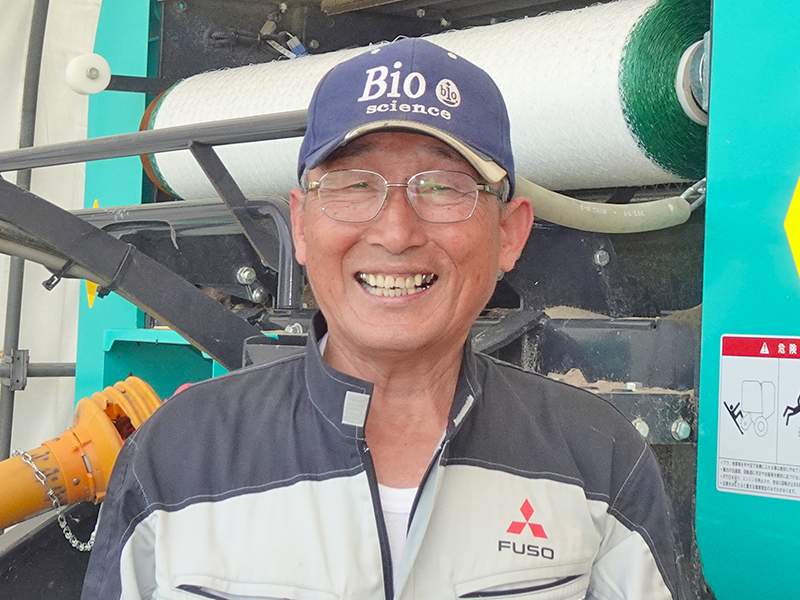
限られた時間と労働力でタイミングを逃さない、効率的な稲WCSの生産が求められる
稲WCSづくりにおいては、嗜好性が良いだけでなく、栄養価も高い高品質のものをつくるため、刈取の時期に気をつかっているとのこと。刈り遅れてしまうと嗜好性も消化も悪くなるという。限られた時間と労働力でタイミングを逃さない、効率的な稲WCSの生産が求められている。
その中で昨年タカキタの可変径ロールベーラVC1620WNを導入した。それまでは外国製のロールベーラを使用していたが、「ピックアップ部がロータリー式なので、そこに青刈りした柔らかい稲が詰まって作業が滞ってしまうことがありました」。詰まった稲を取り除くのには30分以上時間が掛かり、それが1haで5〜6回発生することもあったようだ。その課題解決を模索している時、1haの圃場でVC1620WNの実演が行われ、「ピックアップの部分がカム式駆動になっていて、稲が詰まる様なことはありませんでした。これで購入を決めました」。

昨年同機を導入。現場での実作業でも、「詰まりがなくなって作業を止めることがなくなり、以前と比べて能率が上がりました」と、評価は高い。さらにVC1620WNは作業幅が同社の従来機に比べて20㎝広い、210㎝のワイドピック仕様となっている。作業幅が広くなったことで、「コーナーを回るときには余裕があるので、拾い残しも防げて作業性が良いですね」。
他にも、カッティング部の草詰まりも作業を中断させる要因だが、同機のドロップフロアシステムがその解消に役立っている。「キャビン内から油圧操作でナイフホルダを下げて、簡単に草詰まりを解消できる便利な機能です。特にコーナーでは一度にたくさんの稲が入って詰まる場合があるので、その際このシステムで簡単に解消できます」。効率的作業に繋がる。



Point:ピックアップはカム式駆動を採用しているので、飼料作物を詰まることなくスムーズに取り込む。さらに作業幅が210㎝に広がり旋回時の作業性が向上。
ここが一押し:作業を止めない、国産ならではの使いやすさ。
耕畜連携で資材高騰に活路を
横田さんのベールづくりのこだわりは、高密度のベールに仕上げること。ベールが高密度であることでカビの発生を抑制し安定した品質の稲WCSをつくることができる。さらに、「運搬を考えると、高密度にすることで個数を減らせるメリットもあります」。同機は芯巻きのベルトタイプで高密度なベールができ、横田さんの要望に応えている。また、従来の4本ベルトから新たに幅広2本のエンドレスベルトを採用し、ベールの芯づくりから安定した作業が可能。ベールの密度は10段階、ベールサイズは直径80〜160㎝で調整可能。稲だけでなく様々な粗飼料作物や作業体系に対応する。コントロールボックスの設定は日本語表示で簡単。ネット装着は腰の低い位置からネットを置き台の上に載せて行い、負担が少なく簡単にできる。
実作業を通して、「稲WCSに取り組む生産者には、国産のロールベーラが向いているのではと感じました」とのこと。
今後の展開としては「他の畜産農家にも稲WCSを使ってもらいたいですね。耕種農家にもメリットがあります。そのための橋渡しができればと思っています」。資材が高騰し、生産現場では厳しい状況が続くが、循環型の自給に一つの活路があるのではと感じた。
可変径ロールベーラVC1620WN《主な特長》①作業幅が210㎝のワイドピック仕様。②幅広2本のエンドレスベルトで、ベールの芯づくりから安定作業。③ベールサイズは、φ80〜160㎝、梱包密度は10段階。④コントロールBOXは、わかりやすい日本語表示。⑤カッティング機能で高密度ロールが成形でき、高品質サイレージに調製できる。⑥ドロップフロアシステムを搭載。トラクタに乗ったまま、油圧レバーでナイフホルダを上げ下げするだけで草詰まりを簡単に解消する。⑦幅480㎜のワイドタイヤを装着。⑧カバーが上方に開き、メンテナンスが楽。⑨主要部のローラーチェンは作業中に自動で給油され、グリスアップしづらい箇所は手が届く場所に集中させメンテナンスを容易にした。⑩シェアボルトレスのセーフティクラッチは過負荷によるピックアップドラムの破損を未然に防ぐ。製品説明サイト
㈱タカキタ:〒518-0441 三重県名張市夏見2828 TEL=0595-63-3111

